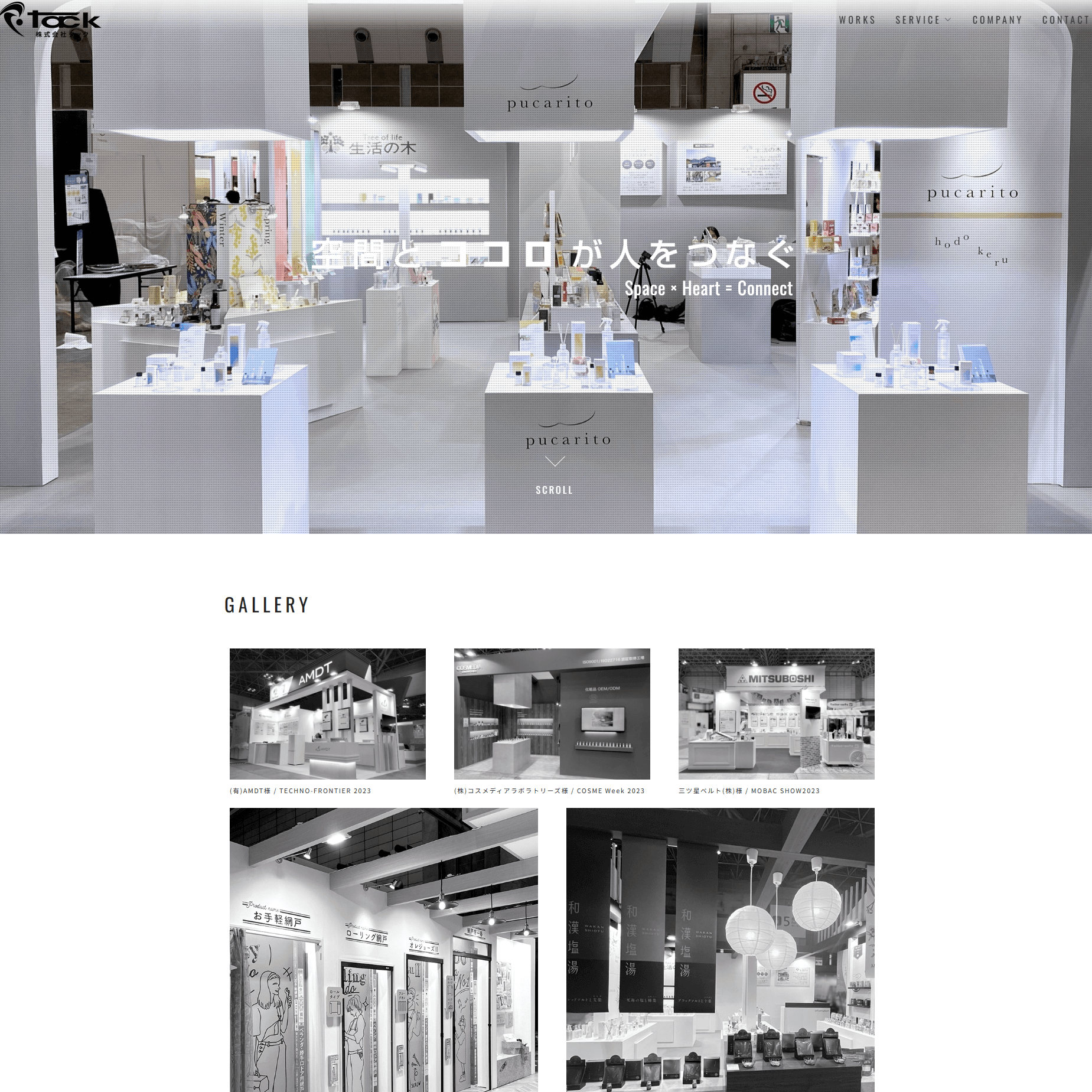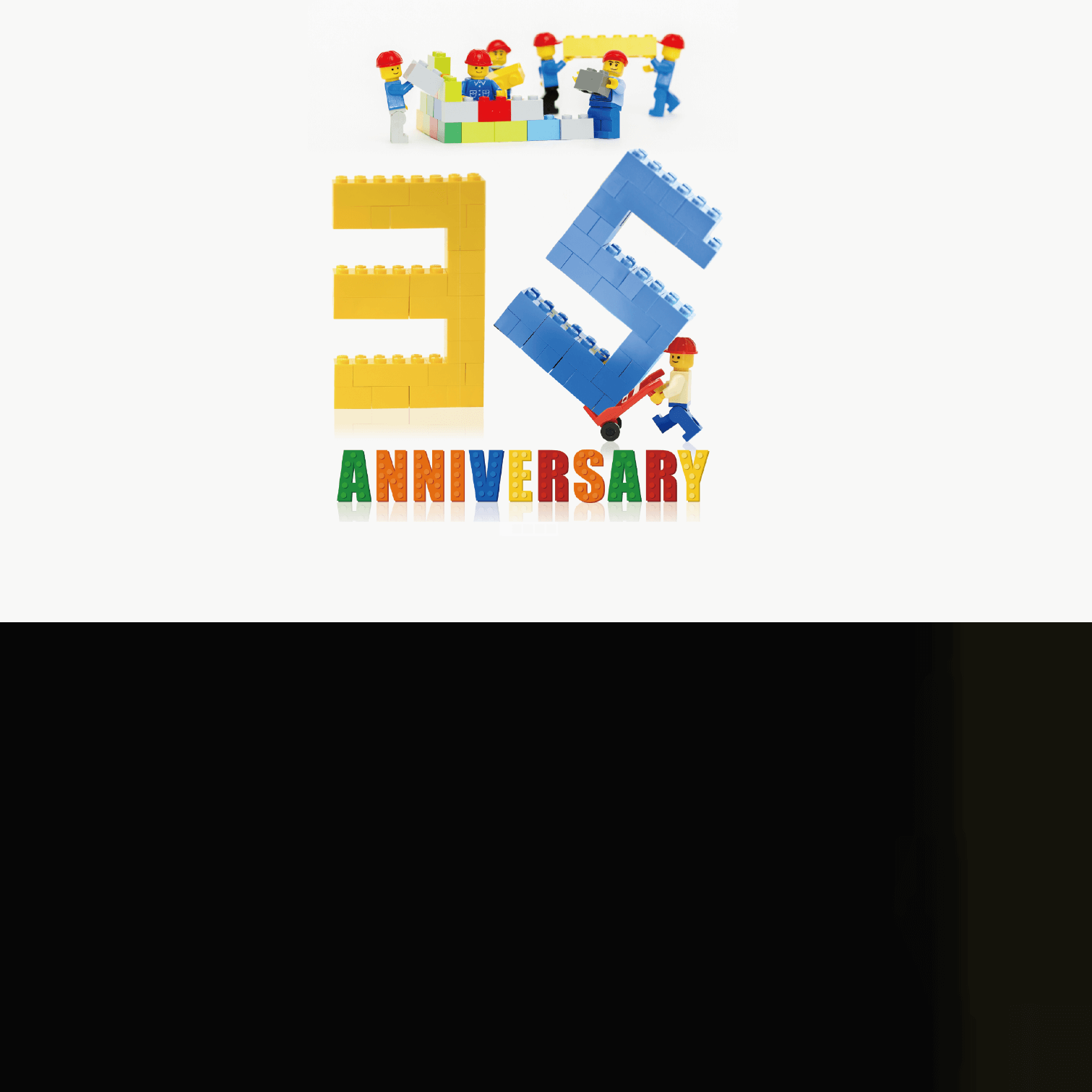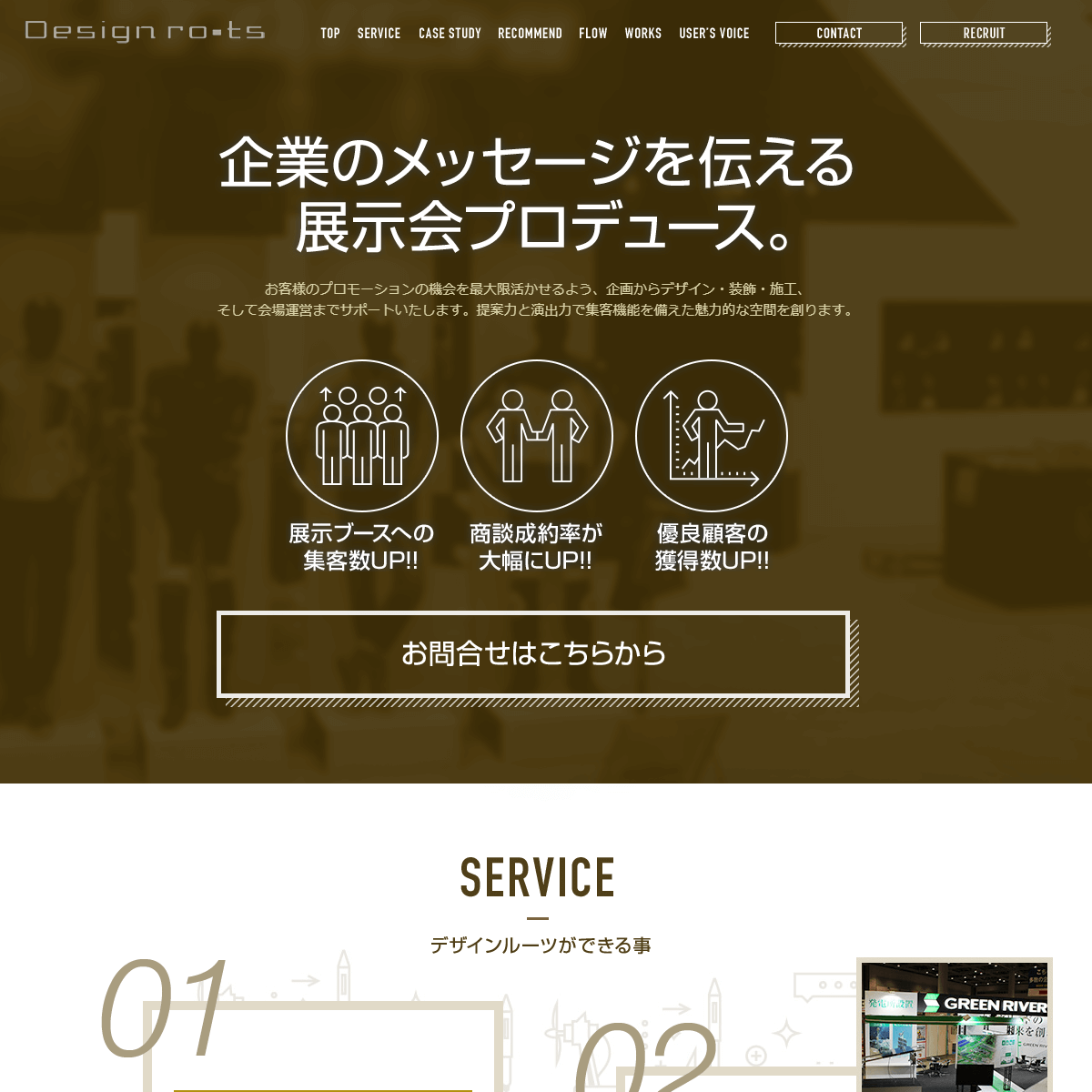展示会で食品を扱ってもいいの?食品を扱う際の注意点とは
 食品を展示会で扱うことは、来場者へのアピール手段として効果的ですが、その際には衛生管理や法律遵守が求められる点に注意が必要です。本記事では、展示会で食品を扱うリスク、さらには注意すべき具体的なポイントについて、詳しく解説します。安全で効果的な展示運営を目指しましょう。
食品を展示会で扱うことは、来場者へのアピール手段として効果的ですが、その際には衛生管理や法律遵守が求められる点に注意が必要です。本記事では、展示会で食品を扱うリスク、さらには注意すべき具体的なポイントについて、詳しく解説します。安全で効果的な展示運営を目指しましょう。
展示会で食品を提供することはできる?
展示会での食品提供は、来場者へのサービスや商品の魅力をアピールするために有効な手段ですが、適切な手続きが求められます。展示会のように、たとえ一時的に食品を提供する場合であっても、食品を扱う以上は一般店舗と同様に営業許可や届出が必要なのです。もちろん、これにはお菓子や加工食品も含まれます。
しかし、実際の営業許可や届出の手続き内容は、自治体によって異なるので注意しなければなりません。調理を行わず、既製品をそのまま販売・提供する場合は届出のみでよいとする自治体が多いですが、不明な点があれば問い合わせて確認すべきでしょう。また、現地で調理を行う場合は自治体の営業許可が必要となったり、営業許可を取得したとしても扱える食品や調理方法に制限があったりします。
そのため、事前に展示会の主催者への相談・確認と出店地を管轄する保健所への連絡、必要な手続きを進めることが重要です。さらに、当日は安全対策を徹底し、食中毒などの事故防止がもっとも重要です。許可や届出を行うだけでなく、提供する食品の取り扱いについても充分注意を払いましょう。衛生的な調理設備の確保や、適切な温度管理、手指の消毒など基本的な衛生管理を徹底することが求められます。
試飲・試食は許可が必要?
展示会で試飲・試食を提供する際に、許可が必要なのかという疑問をもつ人も多いでしょう。実際には、提供方法や食品の種類によって異なる規定が存在します。そのため、適切な準備を行い、関係機関に相談することが重要です。基本的に、食品の提供に関しては、開催会場を管轄する保健所が窓口となります。
ただし、単に届出を提出すれば許可が下りるわけではありません。安全に食品を提供するためには、基準をクリアした設備や環境を整える必要があります。その理由は、衛生的な環境を確保し、食中毒や異物混入といったリスクを防ぐためです。実際の条件では、流し台の設置、テントであれば横幕の取り付け、冷蔵庫など保管設備を適切に設置することなどが求められます。
一方で、食品営業とみなされない場合もあります。たとえば、ひと口サイズの試食や試飲の提供であれば、より簡易的な手続きで済むケースもあります。この場合、要件を満たした届出書を提出するだけで対応できることが多いです。ただし、すべてのケースにあてはまるわけではないため、詳細は保健所で確認したほうがよいでしょう。
無許可でも食品を扱ってよいケースとは
食品を扱う際には、基本的に保健所の許可が必要ですが、例外として許可を必要としない場合もあります。その一例が、密閉された容器に入った缶や瓶の商品です。工場で作られた清涼飲料水や缶詰、レトルト食品などは、製造元ですでに密封・加工が行われており、製造元や消費期限の記載がある場合、販売・配布するだけであれば許可が不要となります。
しかし、このような商品でもその場で栓を抜いて飲ませるなど、提供側が直接調理や加工とみなされる行為を行った場合は、注意が必要です。この行為は調理と同様とみなされ、無許可の場合には違法となるため注意が必要です。許可が不要なケースを活用する際には、密封状態の商品をそのまま提供することに留めなければなりません。また、提供時には商品に問題がないかを確認し、安全な提供を心掛けることも展示会の来場者の信頼を得るために欠かせません。
まとめ
展示会で食品を提供することは可能ですが、営業許可や届出を適切に行い、食品衛生に関するルールを遵守することが前提となります。提供可能な食品や取り扱い条件は自治体によって異なるため、早めに保健所に相談しておくと安心です。手続きと安全対策をしっかりと行い、来場者に安心して楽しんでもらえる食品提供を目指しましょう。