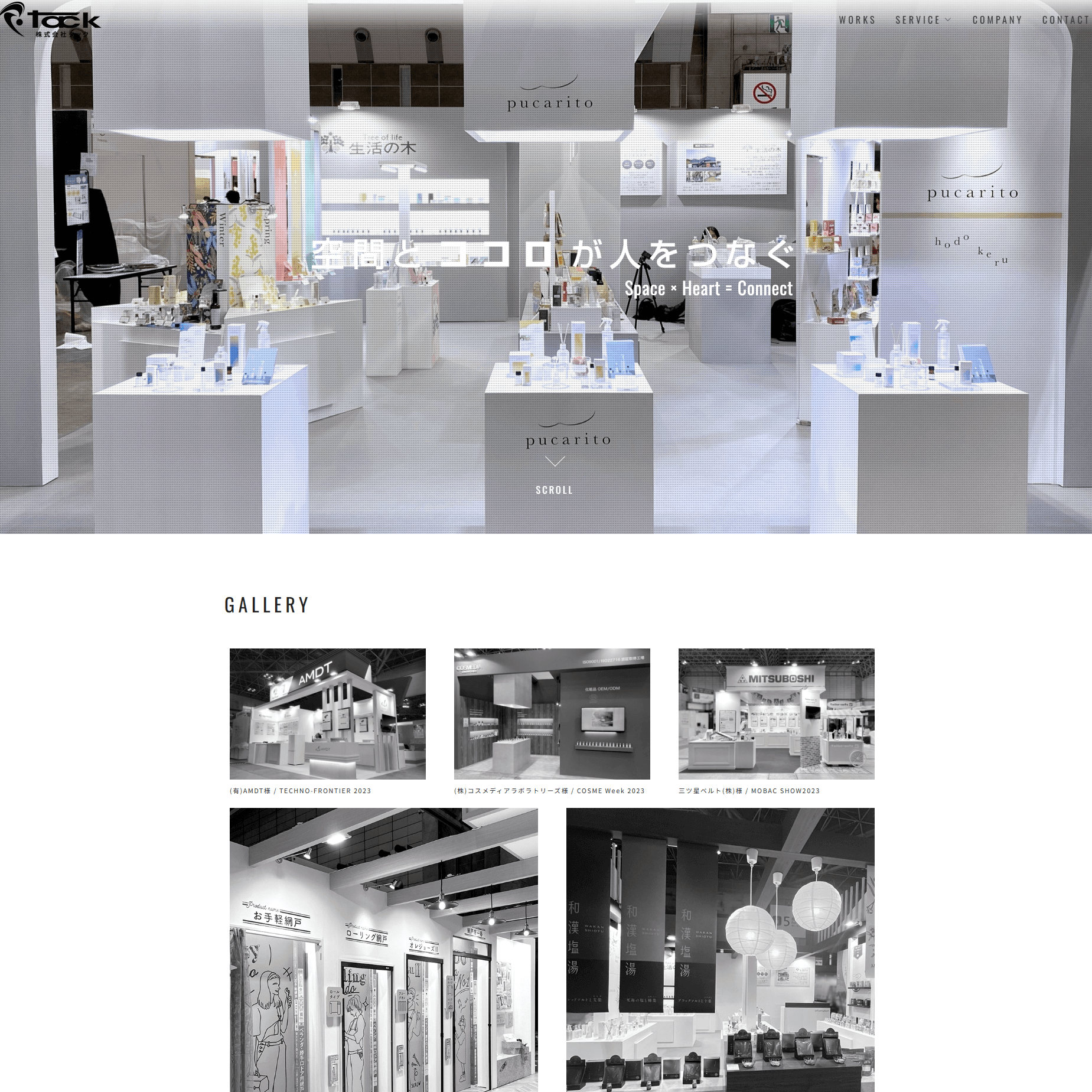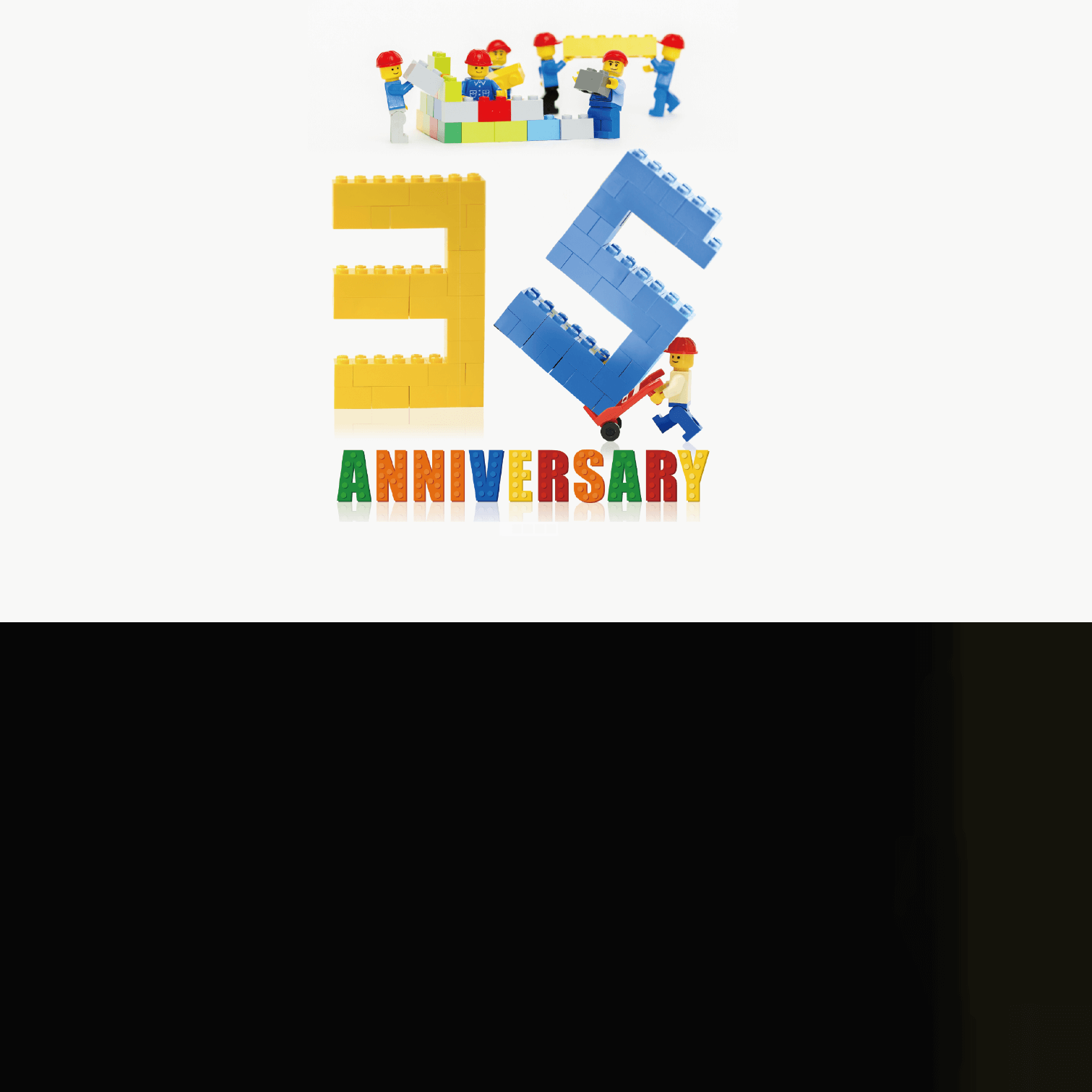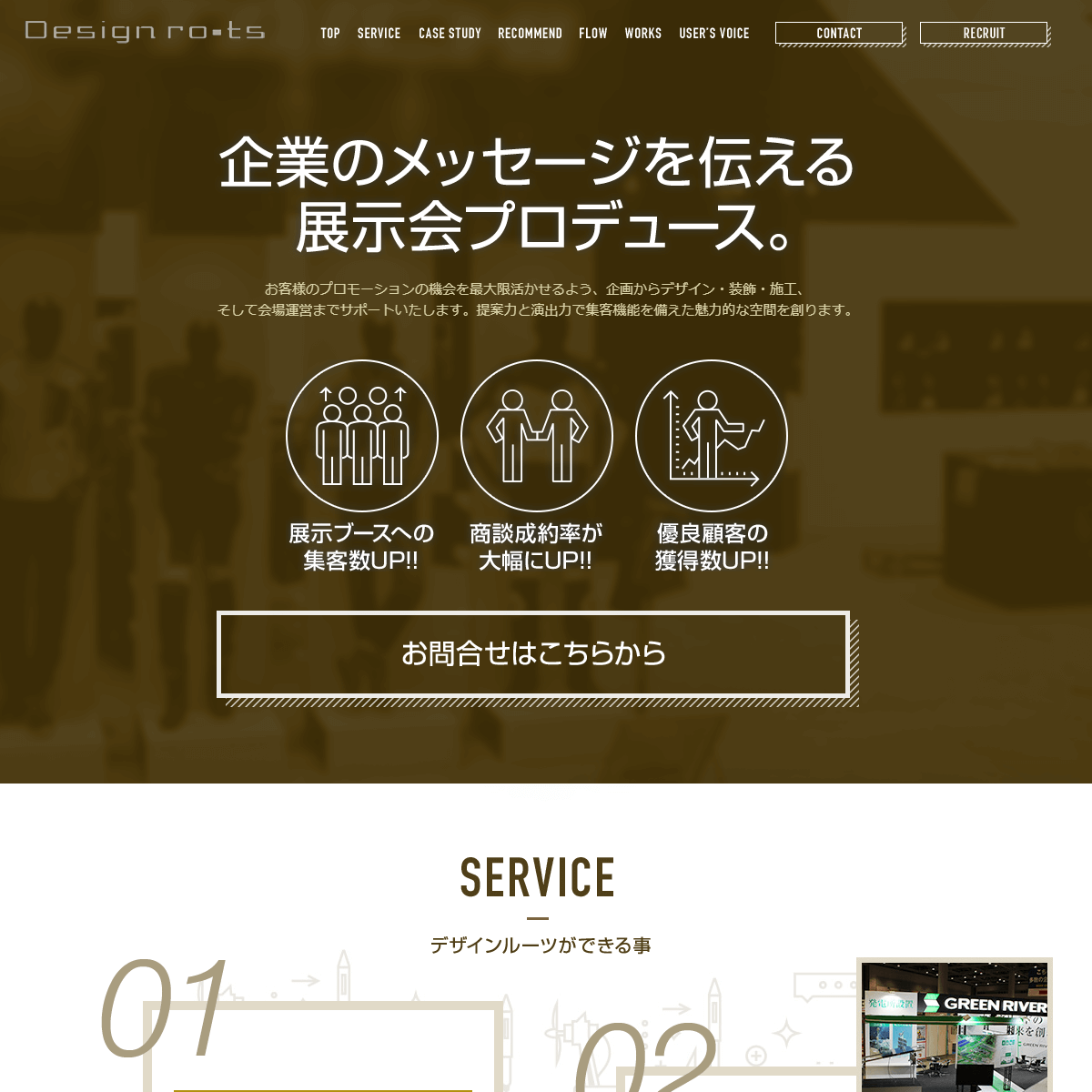日本の展示会はこう変わった!最新動向をチェック

日本国内では、企業同士の商談を目的としたBtoB展示会が長年主流となっています。しかしコロナ禍ではオンライン展示会が急速に普及し、展示会のあり方に変化がありました。近年は再び会場型の展示会が戻りつつあり、出展や来場のスタイルは多様化しています。本記事では、日本の展示会がたどった変遷と最新の動向を紹介します。
日本の展示会はBtoBが中心
日本の展示会は、生活者向けのイベントよりも企業間の商談を目的としたものが多く開かれてきました。特に製造業やIT、建設、医療などの分野では、新技術や製品の発表・商談のために欠かせないビジネスの場として活用されています。ここでは、BtoB展示会がなぜ国内で主流となっているのか、その背景と特徴を見ていきましょう。
BtoB展示会が圧倒的多数を占める
日本展示会協会の調査によると、日本国内で開かれた展示会のうち約94%がBtoB向けで、製造業やIT、建設、医療など業界に特化した商談型イベントが中心です。出展総数は77,000社以上、来場者は740万人を超え、日本の産業に欠かせない場となっています。
主要会場は首都圏に集中
開催地は東京ビッグサイトが約50%で最も多く、次いで幕張メッセが約17%、インテックス大阪が約12%と大都市圏に集中しています。
交通の利便性や設備の充実度が高く、全国から企業や来場者が集まりやすいためです。名古屋や地方都市でも展示会は行われていますが、首都圏が国内展示会の中心地であることは変わりません。
コロナ禍で広がったオンライン展示会
2020年以降、新型コロナウイルスの影響で展示会は一時的に大きな打撃を受けました。その中で急速に広がったのが、インターネットを使って自宅や職場から参加できるオンライン展示会です。ここでは、オンライン化によって展示会がどのように変わったのかを解説します。
時間や場所を問わないオンライン化
オフライン展示会が開催できなかった時期、多くの企業はWeb上で展示ブースを設けたり、ウェビナーを実施したりするオンライン展示会へ移行しました。移動時間や会場費が不要で、来場者も自宅や職場から参加できる手軽さが評価されたことは記憶に新しいです。
過去2年間でオンライン展示会に出展または検討した企業は全体の75%に上ります。
オフラインとの併用が新たなスタンダードに
オンライン展示会は効率面で支持される一方、現物を見て体験できるオフライン展示会の価値も再認識されています。
アンケートでは「今後は両方に出展したい」と答えた企業が約50%を占め、オンラインと会場型を組み合わせたハイブリッド型展示会が増えています。
オフライン展示会は回復傾向
行動制限が解除され、人の移動が活発になったことで、再び会場で開催される展示会が注目を集めています。コロナ禍ではオンライン展示会の便利さが評価されましたが、やはり現地で実物を体験しながら商談できるリアルな展示会の魅力は根強いものです。
ここでは、最新の開催状況と今後の展望について紹介します。
東京ビッグサイトの開催件数が回復
東京ビッグサイトでは2020年に85件まで減少した展示会数が、現在では約240件まで回復しました。企業にとって直接対面で商談できる機会は依然として重要であり、来場者数も増加しています。
現地でのデモ体験やネットワーキングなど、オンラインでは得られない体験価値が強みです。
今後も成長が期待されるBtoB市場
今後も数多くのBtoB展示会が予定されており、リアル展示会は引き続き主要な商談の場として成長が見込まれます。
オンラインの利便性を取り入れつつ、会場での展示や対面交流を重視する動きが加速しています。
まとめ
日本の展示会は長年BtoBが中心であり、東京や大阪など都市部が主な開催地です。コロナ禍ではオンラインが台頭しましたが、対面の魅力を求める声からオフライン展示会は回復傾向にあります。現在はオンラインとリアルを組み合わせたハイブリッド型が増え、企業の展示戦略も多様化しています。今後も展示会は商談の場として進化し、出展社・来場者双方に新たな価値を提供し続けるでしょう。