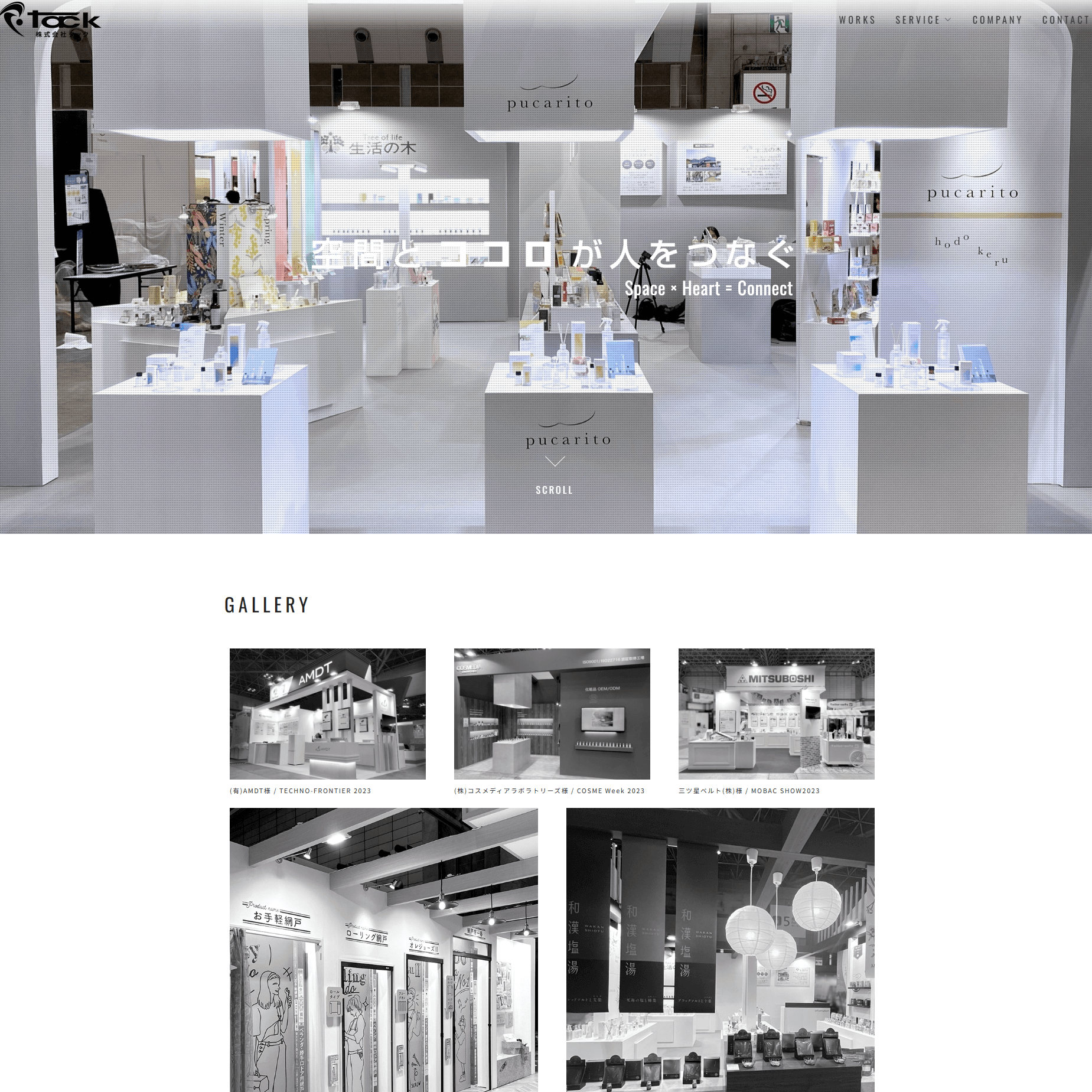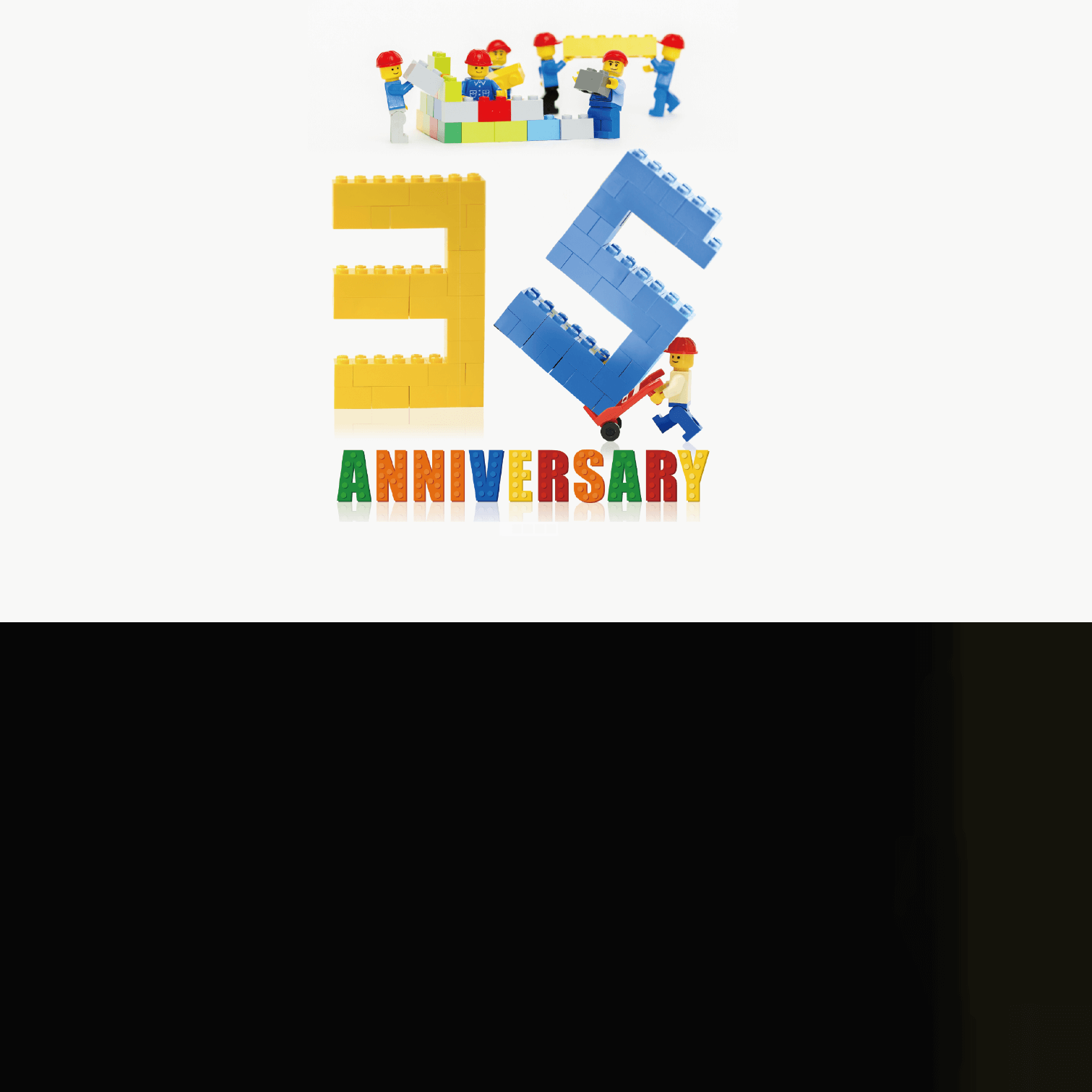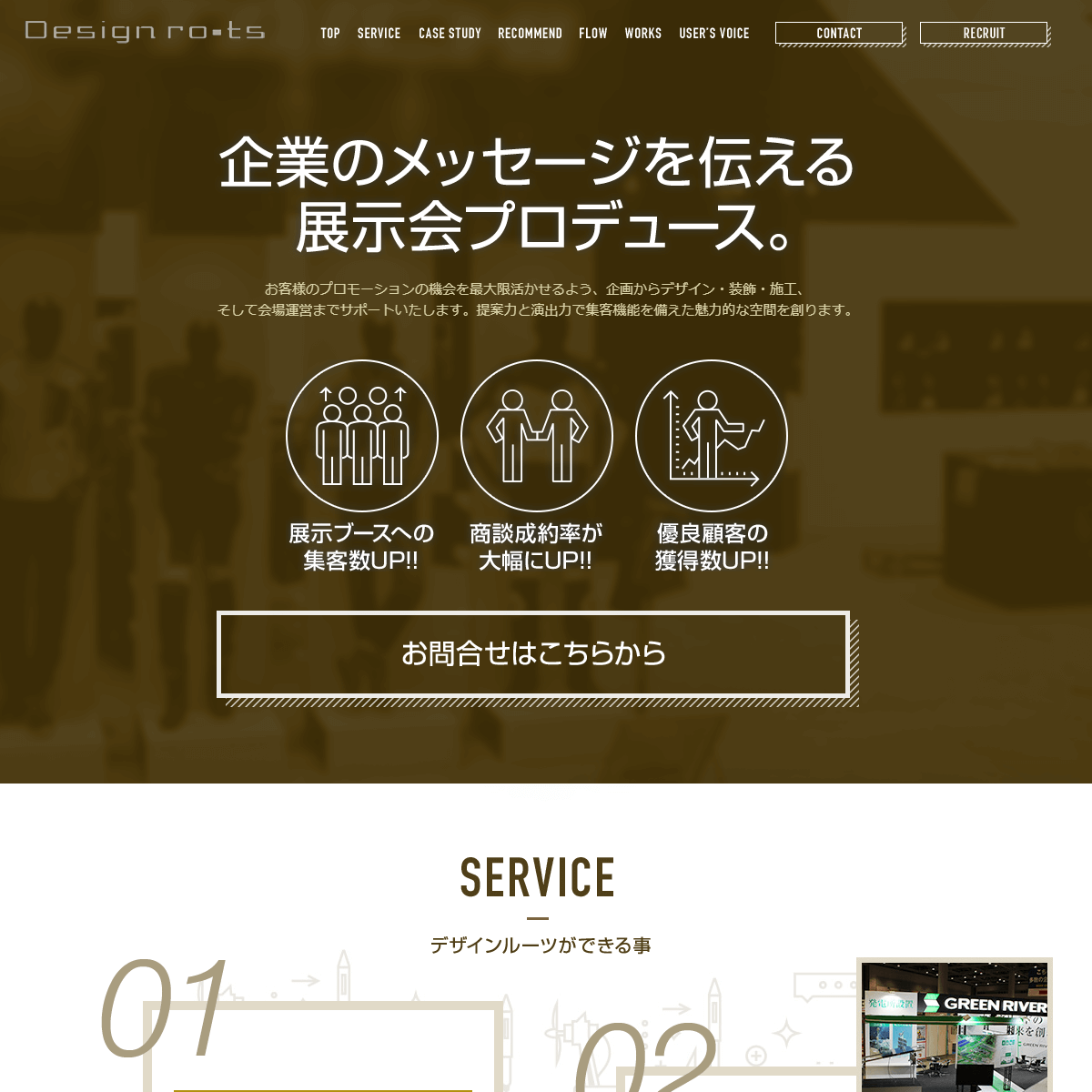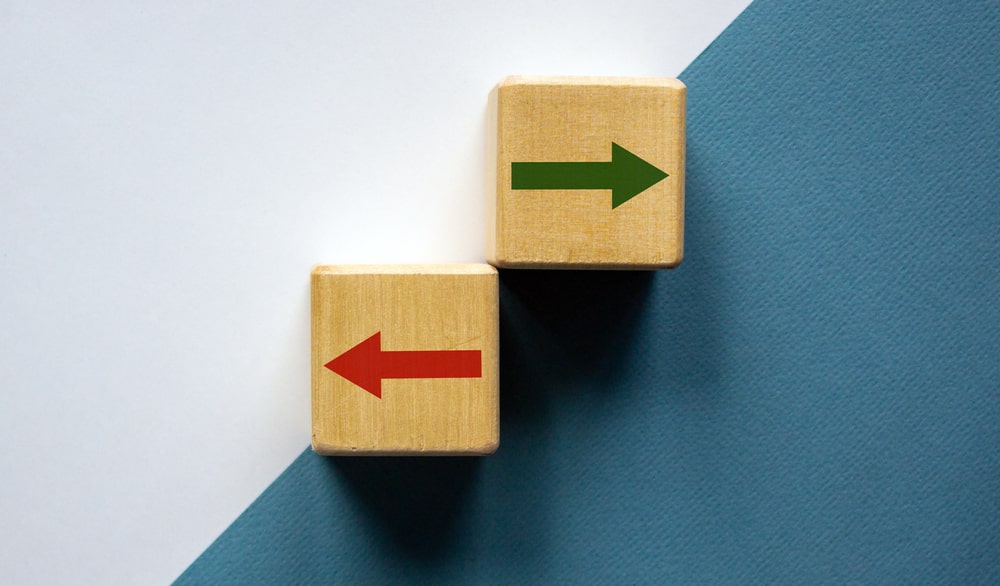リピート率が高い展示会ブース業者に依頼するメリット

展示会ブースは展示物と同じくらい重要なもの。展示会の規模が大きくなるほど参加する企業数も多くなるため、工夫のないブースでは他のブースの中に埋もれ、集客率が下がる恐れがあります。そんなとき頼りになるのがリピート率の高い展示会ブース業者です。今回は、リピート率が高い展示会ブース業者に依頼するメリットをお話しします。
専門業者に依頼すると安心できます
展示会ブース設営を業者に依頼するもっとも大きなメリットは、展示会ブースのデザインや成功するためのコツなどを得られることです。展示会という特殊な空間の中では、場の空気感や特色に合わせたブースを作らなければなりません。リピート率の高い業者は多くの展示会を経験しているため、展示会の出展プランを明確にできます。
また、展示会ブース業者はブース設営だけでなく、企画やデザイン、撤退まで一連の流れについて対応してくれる業者も多くなっています。さらに、経験豊富な業者やリピート率の高い業者の場合、これまでにいろいろなニーズに応えてきた経験があるので、自社の目的をくみとった最適なブースを提案してくれるでしょう。
展示会やイベントなどに慣れていない場合、どんなデザインにするのがよいか見当がつかないケースも少なくありません。そのようなときは専門業者に依頼することによって、デザイン性が高く他社と差別化を図れるブースを手にすることが可能です。
経験豊富な業者に依頼してみよう
東京などの首都圏ではリピート率の高い専門業者も多くあります。業者を選ぶ際には会場自体の実績や経験などをヒアリングしてみましょう。大きいところだと有名展示会場においていろいろなブースを設営した経験があるでしょう。
交通事情や搬入事情などは会場で異なるので、業者が初めて設営するような会場になると不安がありますが、どのように車両を着けてどの出入口から搬入すると効率がよいかなど判断力には経験の差がでてきます。展示会ブース設営は時間との戦いになるので絶対に間に合わせないといけません。
交通事情や搬入などで手間取り、時間をロスすることがないよう、経験豊富な専門業者を選ぶと安心です。東京にはいろいろな展示会ブース業者があり、中にはリピート率の高い業者もあります。興味を持った業者があるなら一度相談してみるとよいでしょう。担当スタッフと話し合っていくうちに得意分野などを把握することが可能です。
リピート率の高さは満足度の高さにつながります
展示会業者を選ぶ場合、リピート率の高さは重要な項目です。他にもいろいろな候補があるのに前回と同じ依頼先を選択するのは、初回に受けたサービスについて納得しているからでしょう。費用対効果が高く、また依頼したいと思えたからと考えることができます。
リピートする顧客が多い業者であれば、信頼できるサービスを提供する証拠だと考えられるでしょう。リピート率が高いとクライアントを大切にしていることにもなり、次に利用する時にスムーズに準備できるよう、過去の記録を残しておいて対応するところは多くあります。適切なプランを用意し、提案してくれる確率が高いです。
展示会ブースの重要性は高く、専門業者に依頼するとブースのデザインや照明の使い方など適切な設置をしてもらえます。出展者が搬入や組み立て、撤収などを行う必要はないため、出展内容や当日の進行に集中できます。
また、リピート率が高い業者は企業からの信頼が高いことがうかがえます。展示会に初めて出展する際には、リピート率を重視して業者を選んでみてはいかがでしょうか。「また依頼したい」と思える業者を選びたいなら、公式サイトや口コミサイト、SNSなどをチェックしてリピート率の高い展示会ブース業者を選ぶようにしましょう。
東京で展示会ブースを設営する場合、ブースの制作を外注することが一般的です。外注する際に特に着目したいのがデザインですが、その設計の流れを理解していれば、どのタイミングでどんなことを確認すべきかが理解できます。こちらでは、自社の目的にかなったブース作りができるように、問い合わせの段階からの流れを説明します。
問い合わせからヒアリングで詰めたい内容
展示会ブースのデザインは問い合わせから始まっているといっても過言ではないため、東京で展示会に出展する場合は、連絡をする際に相談内容などを手元に置いて話をすることが大切です。
大抵の場合は電話やメールで問い合わせができるようになっているので、どんなコンセプトで展示会を行いたいのか、今までの展示会運営で困っていることなどを含め、大まかな内容を伝えるようにします。
そして外注先に連絡を取ると、直接ヒアリングする機会が設けられるため、さらに詳細内容を相談していきます。この段階では、展示会のターゲットがだれなのか、そのターゲットに向けて一番効果的なブースはどんなものなのか、また、来場者に興味を持ってもらいたい商品やサービスのイメージを膨らませ、デザイン作りの骨格といえるものが共有できるようにします。
さらに、展示会に置きたい商品やサービス内容を実際に見て、ブース全体をどのように作っていくかの参考情報を得ていくようです。
情報収集した後のデザインの落とし込み
展示会ブース作りの外注業者は、問い合わせやヒアリングで得た情報をもとにデザインを設計していきます。展示会ブースでは、特に上方に目線が行くことを考えて、天井部分に近い位置のコンセプトを大切にしてデザイン設計をすることが大切です。
出展することで認知度を上げたい企業であれば目立つブースにするようにしたり、来場者にとって利益があることをアピールしたい場合はメリットをアピールする内容の短いセンテンスを記載するようです。さらに、ブースのレイアウトも大切な要素となります。特に東京で開催される展示会は、割り当てられるスペースが限られ、依頼者の要望に添った要素を盛り込むには綿密なレイアウトデザインが重要になります。
例えば、最も注目してほしい商品やサービスを通路側の位置に置くよう設計しつつ、より多くの展示内容を見てもらえるように配置するデザインとします。また、来場者の動線を確保し、一か所に滞留しないようにするなどの工夫も求められます。
デザインを形にして打ち合わせを重ねて調整する
展示会ブース全体のデザインの方向性が決まったら、ラフと呼ばれる完成イメージ画像を作成します。最近では3D画像で立体的に作成し、よりブースのイメージがわきやすいように作成するケースが目立ちます。
これらの画像データを用いて、展示会ブースの依頼主と打ち合わせを行い、ヒアリングなどの際に得た情報をもとにした作成の意図やコンセプトを説明していきます。この話し合いの際には、展示会ブースのテーマや発信したいメッセージを確認し、それを最大限に生かすためにデザインに取り入れたこだわりについても解説します。
その後、依頼主の意見を聞き、修正点や改善すべき点を詰めていきます。この段階になると、展示会づくりに必要な材料のめどが立つので、見積もりが提示されます。さらに、依頼主からの要望や修正依頼をもとに再度ラフや3Dの作成や調整を行い、依頼主に提出されます。そして、依頼主から承諾を受けたなら、展示会ブースの作成の準備に取り掛かります。
展示会ブースのデザイン設計は、依頼主から問い合わせがあった段階から始まっています。特に東京で行われる展示会では、限られたスペースに依頼主の要望を盛り込むことが必要となるため、綿密なヒアリングやラフ・3D画像を用いた確認がポイントとなります。
展示会に出展するときは自社専用のブースを設営してもらうことがほとんどです。
展示会ブースを設営してもらうときは専門業者に依頼することができますが、予算の関係で、自分たちでやった方がいいと考えるケースもあるでしょう。
しかし、業者に依頼することで様々なメリットが得られるようになるのです。
そのメリットについて、この記事では紹介していきます。
ブースの持つ役割は思っている以上に重要
展示会のブースはそれほど重要ではなく、中身で勝負しようと考えるかもしれません。
しかし、展示会ではブースは大変重要な意味を持っています。
展示会も規模によりますが、大規模なものでは相当数の出展企業もいますし、それ以上の来場者が展示会に訪れると予測できます。
展示会にやってきた来場者は、出展しているブース、全てを回るようなことはほとんどありません。
中には、そのような人もいますが大半が自分の知っている企業や、興味のあるブースしか訪れないのです。
そうなると、知名度の低い企業は不利になってしまいます。
そこで、来場者を惹きつけるためにブースが重要な役割を果たしてくれるのです。
ブースを見て、入ってみたい!話を聞いてみたい、と思ってくれると、ブースを訪れる人の数も増えるでしょう。
人を惹きつけるブースは、素人ではそう簡単に考えることはできません。
今までに様々なタイプのブースを設営してきたプロに依頼することで、来場者の興味、関心を惹きつけてくれるようなブースを作ってもらうことができるのです。
目的を的確にくみ取って最適なブースを提案
展示会のブースを設営してくれる業者は、今までにもたくさんの展示ブースを設営してきた経験があるはずです。
顧客によって、ブースに求める要素は異なりますので、経験豊富な業者ほど、そのニーズに応えてきたと考えられます。
展示会に出展する目的も、それぞれの企業によって異なると思いますので業者がその目的を的確にくみ取って最適なブースを提案してくれるようになります。
それも、業者を利用する利点のひとつになるでしょう。
また、初めて展示会に出展するときは、どのようなブースを作っていいのかが自分たちでもよくわからないものです。
そのような場合でも、業者に相談するだけで、目的達成のためにはどのようなブースが適しているのかを様々な形で提案してくれるのです。
業者との話し合いによって、展示会出展に関する具体的なプランを明確にできるようになります。
予算についても相談可能、アフターフォローも安心
また、予算配分についても相談に乗ってもらえるでしょう。
展示会に出展する際には、予算を決めてその中で様々な費用を分配していく必要があります。
展示会出展経験が少ない企業や担当者にとって、何にどれだけの費用をかけていいのかがよくわからないのです。
そこで、業者に相談することで、適切なアドバイスをしてもらえます。
また、ブースに求める要望に応じて、予算内で収められるようにさまざまな努力や工夫をしてくれることもあります。
さらには、アフターフォローも受けられますので、安心して展示会を運営できるようになるでしょう。
展示会の最中にもしもトラブルがあった場合でも、業者に依頼すれば適切に対応してもらえます。
展示会の人員は各社ともにそれほど多くはありませんので、ブースに関するトラブルが起こった時に迅速に対応できるとは限りません。
また、展示会でモニターなどを設置するときに、素人では接続などで失敗してしまうこともありますが専門業者に任せておけば、その点も安心です。
専門業者に依頼すると、費用がかかってしまいますが、それよりも受けられるメリットのほうが大きいのです。
展示会の出展から撤去まで、安心して展示会をすすめるためにも、業者からのサポートは大変心強いでしょう。